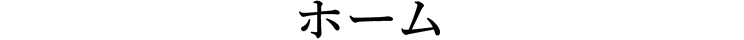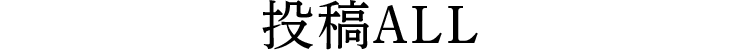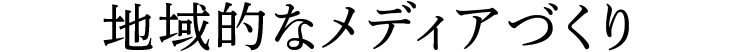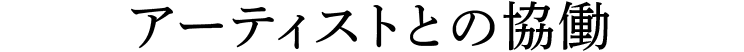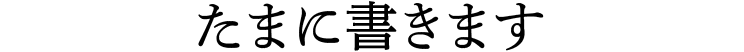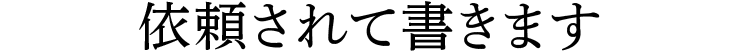2月に益子に滞在し、撮影を行っていた、イタリアの写真家、アレッシア・ローロ。3月に栃木市を拠点に撮影を行っていた、ブルガリアの写真家、ウラジミール・ペコフ。ふたりの写真(膨大な作品点数から一部)を収めた記念誌が「EUジャパン・フェスと日本委員会」より、刊行されました。
アレッシアの現地コラボレーターとして「プロジェクト協力者の眼|A Collaborator’s View」の寄稿を依頼され、アレッシアの滞在中の、とても印象的だったことを書かせていただきました。以下に転載させていただきます。
–
共鳴しあう瞬間
益子は、農業と窯業の「土」の町。土を掘り水で漉し粘土を精製し、山々の木を切り薪を燃して登り窯の火で器を焼く。原初的なマテリアルに向き合いながら作陶をする人が多く暮らす。初来日のアレッシアが、その風土と人々に馴染むのは、とても早かったように思う。蕎麦屋さんでは「とろろそば」を気に入って箸で(私より!)上手に食べ、アレッシアが読んできたという『陰翳礼讃』(谷崎潤一郎)に通じる陶芸家の細工場の囲炉裏で、お茶の時間を楽しみ…。地元の人たちと撮影後に談笑するアレッシアの様子は、もう随分長いこと、この町に住んでいる作家のようにも見えた。馴染むだけではなく、土地の姿を捉える理解も早かった。彼女は「最初はエキゾチックなものに眼がいくけれど、眼を日常的に慣らしていくことで見えてくるものがある」と言う。「この土地では、人の魂と土地と家とがしっかりと共存している」と語るアレッシアの眼を通して、私たちもまた、自分たちが暮らす土地と私たちの暮らし方、生き方を再確認していくような体験となった。
とりわけ印象深いのは、滞在の終盤に陶芸家・佐藤敬さんの工房へ撮影に伺った時のこと。佐藤さんの顔に粘土を少しずつ塗っていく。その過程でポートレイトを撮る予定だったのだけれど、奥様の香織さんと話すうちに感じるものがあったのか、アレッシアは香織さんにも出演を頼んだ。仰向けに床に寝て眼を閉じた佐藤さんの顔に、少しずつ香織さんが粘土をぬり、最後には顔全体を覆いつくす。香織さんの手の所作は優しく美しく、時折アレッシアは細かな指示を出しながら、その濃密な時間を撮り続けた。撮影が終わり、顔の粘土の拭き取りを手助けしながら香織さんの目は涙で潤んでいた。涙のわけについて、アレッシアと佐藤さん夫妻は、工房でお茶を飲みながら語り合った。「日本には、亡くなった家族をおくる時に死化粧をしてあげる風習があって、粘土を塗りながら、いつかはそんな日が来ると思うと少し悲しくなって」と話す香織さんに、優しく頷くアレッシア。生と死は隣り合わせ、命の終わりがあれば、また生まれてくる命があること、日本の『古事記』で語られた国づくりの伝説や、泥から人が作られたとする聖書の話など…、国境を越えて「根源的な、なにか」のことを語り合った。香織さんは別れ際に「ただ撮られるということではなくて、作品を作ることに参加するって、こういうことなんですね」と穏やかな表情で伝えてくれた。私も、イタリアからやってきたアレッシアとこの土地の人々が、写真家と被写体という関係性を越えて、たしかに共鳴しあっている瞬間に幾度となく立ち会えたことを、とても嬉しく思う。
.
『EUROPEAN EYES ON JAPAN VOL.21 JAPAN TODAY』より
(EUジャパン・フェスト日本委員会 発行2019/07)